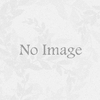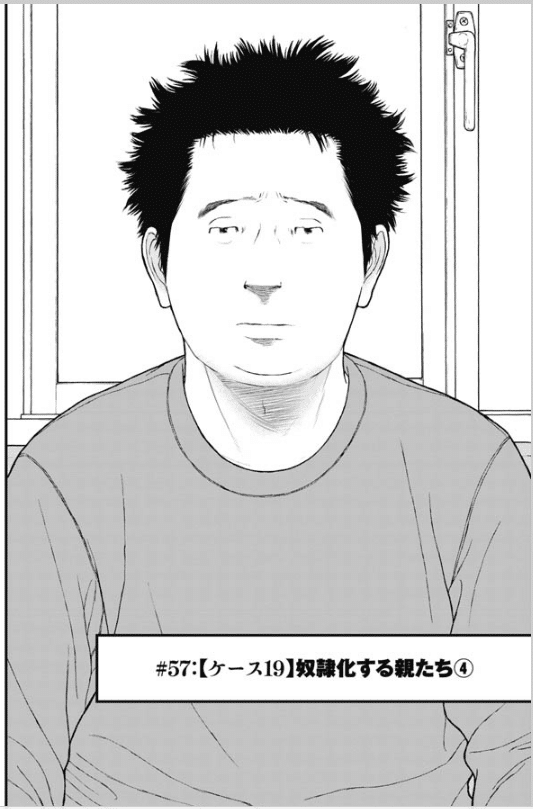俺が唸った! 名言 その4
「企みのある女は、子どもを産んじゃいけないよ。
悪魔の子を産んじゃうからね」。
(ピンクのばあちゃん…元銀座のクラブママ)
昔、住んでいたマンションに、「ピンクのばあちゃん」という住人がいた。
年は80歳近く、どんな時でもピンクの服を着ていた。
俺は、その雰囲気から、おそらく水商売をやってきたひとだろうと予想していた。
それも普通のホステスというよりは経営者で、
着ている物や装飾品の質からも、現役時代はそれなりに稼いできたのだろうと思われた。
見るからに変わり者だったこともあり、
マンションの住民は、「ピンクのばあちゃん」をほとんど無視していたが、
俺は入り口ですれ違ったり、一緒のエレベーターに乗ったりしたときには、
必ず挨拶をするようにしていた。
「ピンクのばあちゃん」は、そっけない挨拶を返してくるだけだった。
住民から距離を置かれていることは、本人も自覚していただろうから、
俺に対してもそんな対応なのだろう……と思っていた。
しかし俺は、彼女の眼差しに、どこか鋭さを感じてもいた。
俺を見透かしてやろうというような……得体の知れない感じがあった。
こうして顔を合わせるたびに、俺と「ピンクのばあちゃん」の間には、
互いを推し量るような、ヒリヒリとした空気が漂った。
そういうことが一年くらい続いただろうか。
俺はある朝、「ピンクのばあちゃん」がマンションの前で、
黒塗りの高級車を見ていることに気づいた。
車は、マンションの隣にある一部上場企業の本社に吸い込まれていく。
俺は何となく興味がわき、別の日の朝、
やっぱり高級車を隠れて見つめる「ピンクのばあちゃん」を隠れて見つめた。
すると車に、その一部上場企業の、会長らしき人物が乗っているのが見えた。
この会長は、世界的に有名な創業者でもあるため、俺も顔を知っていたのだ。
そしてまた別の日、たまたま仕事が早く終わり、
明るい時間にマンションへの道を歩いていたときのことだ。
今度は、例の黒塗りの高級車が社屋から出てくるところに遭遇したのだが、
「ピンクのばあちゃん」は夕方にも、マンションの前で車を見送っていた。
それどころか、車に向かってウインクまでしていたのだ!
ここで俺は、ピーンと来た。
おそらくこの「ピンクのばあちゃん」と、この会長は、恋仲なのであろう。
彼女が水商売をやってきたという俺の予想と照らし合わせれば、そういうこともあり得る。
俺は、「ピンクのばあちゃん、スゲーひとかも」と思い、
気づいた事実は胸に秘め、それ以降も普段通りに挨拶を交わしていた。
それからしばらく経ったのちの、ある休日のことである。
突然、俺の部屋のインターホンが鳴った。
ドアスコープを除くと、「ピンクのばあちゃん」が、「私だよ、早く開けなさい」と叫んでいる。
「なんで俺の部屋が分かったんですか」と言いながら、俺はドアを開けた。
「ピンクのばあちゃん」は、それには答えず、一方的にまくし立てた。
「あんた、この間、テレビで観たよ。凄いことしてるね。
あんた、顔はイマイチだけど、良いオーラ出てるもんね。
あんたの仕事は、企みながら生きている家族から依頼を受けて、やってるんだろ。
そりゃあ、あんたみたいな感じの人間じゃないと、あの仕事はできないわね。
私が見抜いていた通りだったわね。ふふっ。
あんたこの先いい男になるから、ずっと今の仕事をやって行きなさいよ。それじゃーね」
「ピンクのばあちゃん」は、言いたいことを言うと、去って行った。
ラフな感じのいでたちだったが、やっぱりピンクの服を着ていた。
その頃はよく、俺の仕事の特集がテレビで放映されていたので、
彼女もそれを観たのだろう。
その言葉には人間味があふれていて、俺は嬉しかった。
それにしても、すごい勢いだったな。
80歳のばあちゃんとは言え、カチコミに来たのかと思ったぜ。
それからは顔を会わせるたびに
「あんた、将来は絶対にいい男になるよ。私の目に狂いはないからね」と、
口調は厳しく、しかし表情を緩ませながら言ってくれた。
俺は挨拶のあとに「ありがとうございます」と付け加えるようになった。
そしてまたしばらく経ってから、俺は再び、
「ピンクのばあちゃん」がウインクしている場面に遭遇した。
彼女は高級車を見送ると、つかつかと俺の元へ歩み寄ってきた。
そして、俺が以前から二人の関係に気づいていたことを知っていたかのように、
「あのひとの家族は誰も知らないんだよ。私とあのひとの関係は。
あのひとが、会社の隣に住めって言って、このマンションを買ってくれたのよ。
私さ、銀座でお店をやってたんだけど、あのひとに気に入られて愛人になったの。
タイプじゃなかったけどお金持ちだったから、そうなったんだよね。
でも私は銀座のおんなだから、口はかたいからね。
この年になっても、一切あのひとの家族にはバレてないわよ」
「そんな話、俺みたいな人間に話して大丈夫なんですか」
「あんただから言ってんのよ」
「分かりました」
「私、あのひととの間に、ひとり、子供がいるんだよね」
「えっ! お子さんは父親のこと知ってるんですか?」
「教えてないわよ」
「……」
「だから、どうしようもない子供に育ってるわよ」
「父親はあんなに立派なのに、ですか?」
「父親はどうでもいいのよ。
企みのある女は、やっぱり子どもを産んじゃいけないのよ。
悪魔の子を産んじゃうからね」
「えっ!?」
「企みがあったから、銀座で店もやれたし、お金にも困らなかった。
金持ちの愛人やって、子供まで産んだってことでわかるだろ」
「あ、はい」
「あんたのところに依頼に来る家族は、企んで生きてきた母親ばっかりだろ。
私が言っているんだから、間違いないよ」
「分かりました」
「あんたは良い人間だよ。
あんたの母親は、私と違って何の企みも持たず生きてきた女なんだろうね」
「あ、ありがとうございます」
「だけど、女は企みながら生きるのが好きだし、これから先は、どんどんそんな女が増えて行くよ。
だからあんたは、この仕事、ずーっと続けて頑張ってやんなさいよ」
「わかりました」
「それじゃーね」
もう10年以上前の話である。
この会話を交わした二年後くらいに、「ピンクのばあちゃん」は亡くなった。
そして時期をあけずに会長も亡くなったことを、俺は新聞で知った。
俺はあれからもずっとこの仕事を続けてきて、
「ピンクのばあちゃん」が言っていた言葉を、折に触れて思い出すことがある。
全部が全部、そうだとは言わないが、
「企みのある女は……」の言葉がピタッとあてはまる母親は、少なくなかった。
母親自身も分かっていて、「子供より仕事が大事だった」「子供なんて産むんじゃなかった」と、
涙ながらに、俺に本音を言う。
そしてこれは、一世代だけの話ではないことも感じる。
そういう企みのある女性が産んだ子供もまた、
同じように企みを持って子供を産んでいるのだ。
どうしてそうなるのかという細かい分析や説明を、ここでするつもりはない。
現実・事実のひとつとして、そういうことがある、ということだ。