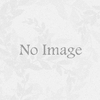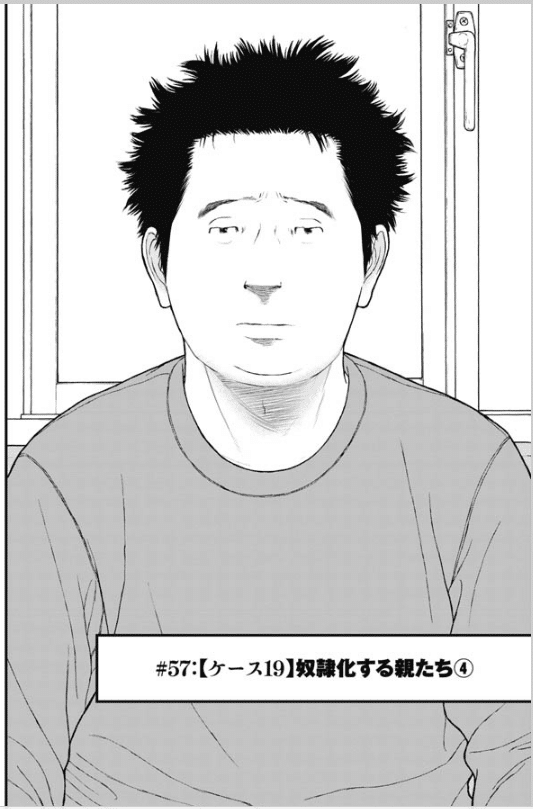白熱インタビュー~アメリカメディア③
アメリカメディアの取材について、追記しておく。
昨年末から今年の正月にかけて、俺と何度も大喧嘩になり、決別した
アメリカメディアのプロデューサー(Ms.マンダナという)だが、
「やはり日本のHIKIKOMORIについて、真実を話してくれるのは、
Mr.押川しかいないので、なんとか話しを聞かせてほしい」
と言って、再度、取材の申し込みをしてきた。
「すべてではないが、日本のカルチャーも少しは分かってきた。
勝手なことを言って、本当に申し訳なかった」と、深々と謝罪もされた。
「Mr.押川のインタビューが撮れるまで、アメリカに帰るつもりはない」
とまで言う。今回の取材を完遂するために、腹を決めたのだ。
俺は、Ms.マンダナのハングリー精神に、恐れ入った。
ちなみに、Ms.マンダナはまだ31歳で、俺よりも若い。
その若さで、猛然とキャリアアップを重ね続け、
今の会社から、超好待遇でヘッドハンティングされるほどの、
シニアプロデューサーであり、ジャーナリストでもある。
俺は、Ms.マンダナのこれまでの振る舞いには腹を立てていたが、
同時に、自分が31歳の頃を思い出していた。
俺もMs.マンダナのように血気盛んで、ハングリー精神をもち
危ないところでもどこでも、突っ込んでいった。
若かった当時は、金がほしい、女にもてたい、そういう気持ちもあった。
しかし何よりも、「自分にしか見つけられない真実」を見つけたかった。
Ms.マンダナも、そうなのかもしれない。
そんなことを、冷静に思う俺がいた。
ともかく、自分より若い人間が、過ちを認めて頭を下げてきたのだ。
きちんと応えるのが、スジである。
「よし、わかった」
俺はそう言って、例の「THE説得」の映像使用について
TBSの担当者に連絡をとり、話し合いの席を設けてもらった。
こればかりは、俺の一存で決められることではない。
TBSとアメリカメディアとの合意と契約が大前提なのだ。
TBS側は、とても大人の対応をしてくれた。
取材に協力してくれた家族も納得できるかたちになるよう、
多大なる尽力をしてくれた。
Ms.マンダナも今回は、日本のカルチャーを尊重し、
先方にも、きちんと敬意を払っていた。
その結果、いい感じで、話しがまとまった。
それから、『「子供を殺してください」という親たち』
の書影も撮りたいというので、新潮社にも足を運んだ。
ここでも、いいかたちでの話し合いができた。
その後、事務所に戻り、インタビューの撮影となった。
Ms.マンダナからの質問は、かなり本質を突く、鋭いものばかりだった。
日本のメディアでは、絶対に踏み込んでこないところにまで、
ぐいぐいとえぐって、球を投げてくる。
「ここまで聞いてくれるのか!」
と、ある種の感動さえ、覚えた。
だから俺も、魂を込めて真剣に、本当のことを包み隠さず応えた。
最も大事な、俺の「志」も、熱く語った。
「THE説得」や著書を掘り下げるような、
いいインタビューができた。
Ms.マンダナも俺も、大満足のインタビューとなった!!



今回のインタビューは、fusion社のベーシックケーブルネットワークと、
動画配信サービス(アップルテレビ、Roku、Hulu、Sling TVなど)や、
その他fusion社のデジタルネットワーク等(ウェブサイト、
fusion you tube チャンネル、fusion Snapchat)で放映される。
俺は、今の日本の、深刻な問題を抱えている家族の現状が、
アメリカでどう捉えられるのかが、とても楽しみだ。
メンタルヘルス・精神科医療については、
やはり欧米のほうが、圧倒的に進んでいる。
アメリカの専門家がどのような意見をいうのか。
アメリカでも増えはじめているHIKIKOMORIの問題を、
どう解決しようとしていくのか。
今回のインタビューをきっかけに、
それらの情報が手に入るのではないかと期待している。
ここに至るまで、Ms.マンダナと俺は、
何度も何度も何度も、激論を交わした。
殴り合いこそないが、さながら命がけのケンカであった。
間に入っていた日本人プロデューサー兼コーディネーターや、
日本人カメラマンの方も、非常にハラハラし、
頭を抱えながら、この一ヶ月を過ごしていた。
しかし、とことんやったケンカにはひとつだけ、いいところがある。
それは、仲直りができることだ!


Ms.マンダナは、別れ際に言った。
「日本のためになるのなら、Mr.押川が訪米した際には、
私の知っているメンタルヘルスの専門家を紹介します」
「私はこれからも、HIKIKOMORIについて、取材を続けます。
最先端の情報を、お互いに交換しあいましょう」
俺は、そのMs.マンダナのこころからのメッセージに、感謝の言葉を返した。
Ms.マンダナの心のシマに、俺のシマができた。
俺の心にも、Ms.マンダナのシマができた。
もちろん、間をつないでくれて、奔走してくれた
日本人プロデューサー、カメラマンのお二人にも、大感謝だ!